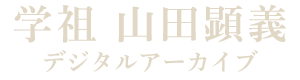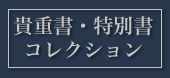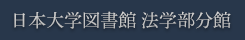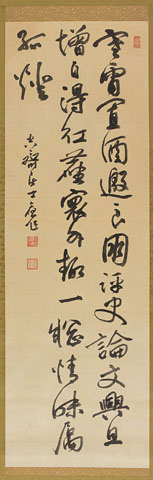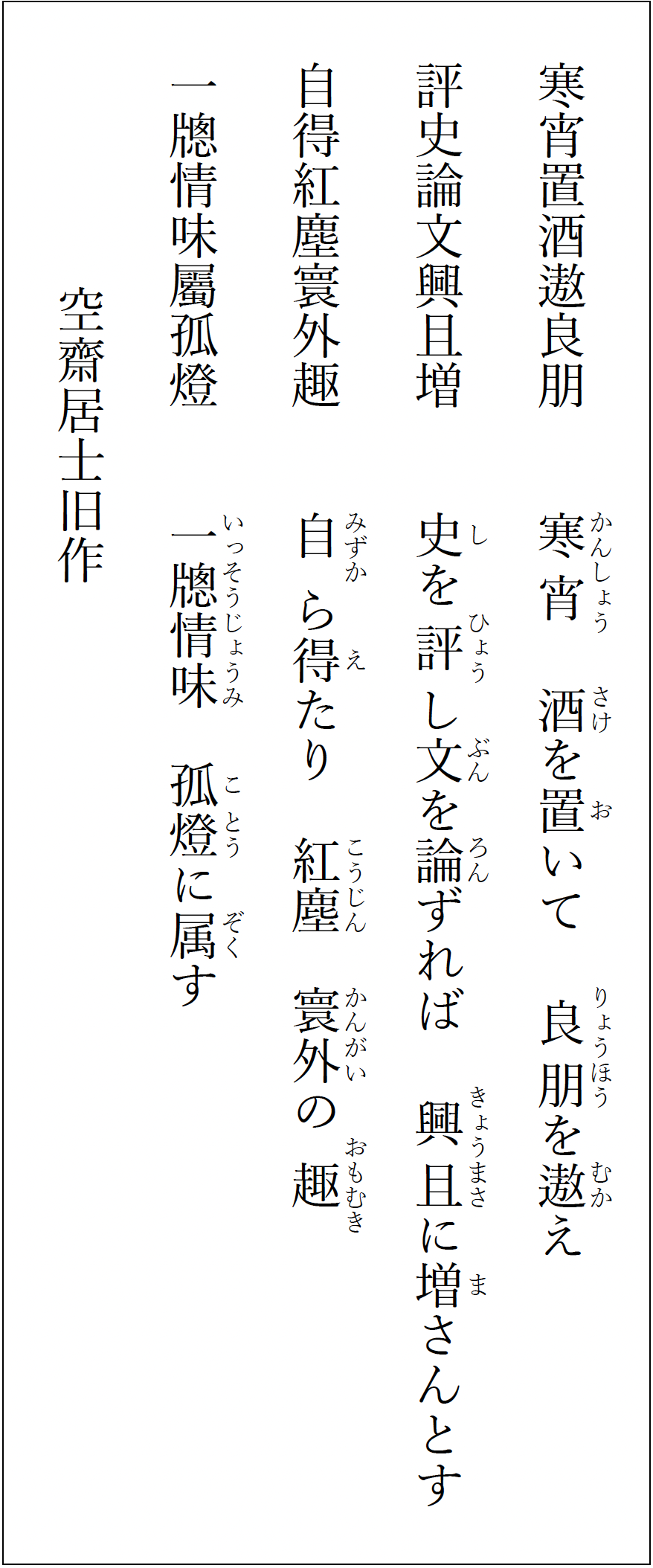山田顕義七言詩 (絹本墨書) (作間介堂来訪し酔餘のうえ韻を分つ)
[大意]
冬の夜、酒を用意して、親友を迎え
歴史や詩文を評論し合っていると、詩興が湧いてくる
知らず知らずに浄化される、俗塵を脱却した境地は
一つの窓にぽつりと映る、灯火の風情
[注]
- 【寒宵】
- 寒い夜。
- 【置酒】
- 酒を準備すること。
- 【良朋】
- 親友。
- 【紅塵】
- 都会の雑踏による土埃。俗世間を象徴する詩語。
- 【寰外趣】
- 俗界を逸脱した高雅な興趣。「寰外」は圏外。「趣」は文人同士の愉しみ。
- 【一牕】
- 牕は窓の異字体。
[補説]
「空齋詩稿」137頁の一四四に「作間介堂來訪醉餘分韻」の詩題が付いていることから、この詩の第一句の「良朋」が作間介堂(作間正臣)(1846~1884)であることがわかる。作間正臣は長州藩士。通称は一介、介堂と号した。明治初期に太政官の史官となり、明治10年に権大書記官、同17年には元老院議官となっている。詩や書に通じていたという。