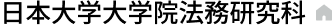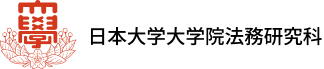研究科長挨拶

実務家に必要な事案分析力,論理的思考力,社会常識に照らしたバランス感覚を丁寧な双方向授業で培えます。
日本大学は明治22年(1889年)に日本法律学校として開学以来,法曹界に多くの人材を輩出してきました。この130年の長きにわたる伝統と「自主創造」の教育理念のもと,日本大学法科大学院では社会で高い能力を発揮できる法曹養成に取り組んでいます。法曹の能力は,具体的な紛争にあたって,如何に適切な解決策を導き出せるかにほかなりません。その力とは,事案についての法的視点からの分析力と論理的な思考力,そして,事案の解決策が社会規範から乖離せず,社会常識に照らし合わせて整合する,バランス感覚を備えた判断力であると言えます。
こうした力を具備した法曹人を養成するために,カリキュラムに工夫をこらしています。授業は双方向の参加型学修を重視し,その学修効果を最大限に高められるように少人数の授業にしています。例えば,事例問題を課題とし,予習により得た知識と,解決策を導いた法的思考プロセスの是非を論じるなど,授業では学生に発言を多く求めていきます。つまり,その結論に至る根拠とした条文や判例規範について,学生一人ひとりの思考を確認しながら,具体的な事例の解決から法律を正しく理解できるように導いています。同時に,実務家に欠かせない口頭による表現力と文章による表現力,のいずれも兼ね揃えた法曹人になれるように指導しています。
実務家としての力を高めるために,法律実務基礎科目を重視しています。例えば,「民事訴訟実務の基礎」では以前の司法修習制度における教育を念頭に置いて,要件事実教育を手厚く学べるようにしています。事案に含まれる事実関係から,請求原因を導くことや反対に抗弁を検討するなど,実務家に欠かせない多面的な思考力を培っています。
日本大学は,文理にわたる広範な学問領域で研究を進めていますが,この総合大学のスケールメリットを生かし,法分野の中でも専門性が求められる領域を深く学ぶことができます。とりわけ「企業法務」,「医療」,「知的財産」,「環境」及び「労働」の5分野は,いずれも現代社会が法曹にその専門性の発揮を強く求めている分野です。実務に就いたときに,特色を持つ法曹として活躍する基礎を築けます。
そのほかに,入学前教育,司法試験合格者である助教との相談(アカデミック・アドバイザー制度),教員のオフィスアワー,最適な自習環境,学生生活・就職委員会による合格後の就職フォローなど,法律の学修に集中できる環境や,工学部などを卒業した完全未修者を合格に導くなど,基礎から応用まで安心して学べる環境も整えています。
日本大学大学院法務研究科長 小田 司